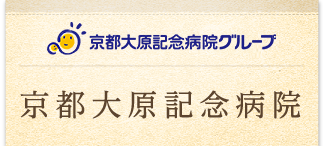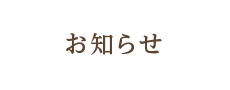副院長の三橋尚志が、一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会 会長に就任しました!
京都大原記念病院 副院長の三橋尚志医師が、2019年5月16日付けで一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会(以下、協会) 会長に就任しました。今回はその記念インタビューをご紹介します。 ―まずはこの度の会長就任おめでとうございます。率直な心境をお聞かせください。 大役を仰せつかり身の引き締まる思いですが、背伸びをせず自分ができることをしっかりとやっていきたいなという気持ちです。 協会には2003年から理事、2013年から常任理事として関わって来ました。協会としてはこれまで、診療報酬や実態調査の分野などに注力して来ていましたが、自分自身もこれまで関わる事の多かった「教育・研修」面をより一層充実していけるようがんばりたいと考えています。 ―当院は一般病院、老人医療、リハビリ医療へ回復期リハビリへと転換してきました。こうした転換を振り返るとどのように感じられますか? 私は1982年に医師になりました。当グループのスタートとほぼ同じ時期です。縁あって1991年に当院に着任した当初、病院としては「老人医療」が中心でした。 診療の中心は合併症を予防し、療養を支援することでした。しかし包括的なサポートが必要ななかで出来高制でしか対応できなかった点については「老人医療の限界」「出来高制でのジレンマ」も感じていました。 90年代から介護力強化病棟、完全療養型病床群が生まれ包括的に対応する仕組みが生まれ始めました。92年にリハビリテーション総合承認施設として基準をクリアしたことも非常にタイムリーだったように思います。(その後、2000年に回復期リハビリテーション病棟の制度化と同時に同病棟へ)私の専門は整形外科ですし、かねてからリハビリテーション(以下、リハビリ)には興味がありましたのでリハビリ医療を中心に展開するという方針には手放しで賛成しました。 ―当時、いろんな苦労や驚きなどはあったのではないでしょうか? 苦労した点を一言で言えば「人集め」です。病院として打ち出そうとする特徴の「リハビリ」の認知も低く、リハビリのために入院するという概念がありませんでした。急性期病院など医療関係者においても同様です。こうした背景もあり、患者さんにしても、看護師などのスタッフにしても集めるのはとても大変でした。 私自身も「リハビリの底力」に驚かされました。その当時、高齢者のリハビリはあまりクローズアップされていませんでしたが、大原でセラピストがやってくれていることを目の当たりにして「ここまでよくなるんだ」と驚いたのは今でも覚えています。 日本は平均寿命が世界一、医療レベルも高い水準です。しかし、当時は寝たきり患者も世界一多かったのではないかと思います。国もこれを背景に、90年代前後からゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略・1989-)、新ゴールドプラン(同・1991-)で「寝たきり老人ゼロ作戦」などの施策を展開されました。そのタイミングでの転換であったので、国の施策ともマッチしたものであったと捉えています。 ―現場では医師や、看護師、セラピストに混乱はなかったのでしょうか? 特に看護師はリハビリによって実際に状態が良くなる様子を近くで目の当たりにして意識が変わっていったように思います。 当時私を頼って手術を受けに大原に入院していただいた一人の患者さんからお叱りをいただいたことが印象に残っています。手術後にT字帯ではなくオムツを付けられたことで「こんな年寄り扱いして、こんな病院二度と来ない!」と強く言われたのです。 それまで寝たきりの患者様が多かった病棟では当たり前にしていたことも、目的や意思を明確に持って手術やリハビリを受けに来られている患者様にとっては相当のショックであったようです。以降は病棟内でも意識を変えて、看護師を中心に工夫してもらいました。有難いことに、その患者さんはその後も大原で入院して手術を受けられています。 ―そうした過程を経て現在の姿に至る京都大原記念病院の強みについてはどう捉えていらっしゃいますか? 当院は市街地から離れていて、人口が少なく、建物も老朽化してきている・・・決して恵まれた環境ではないかもしれません。 その条件下で、急性期病院などから紹介をしてもらうためには確実に結果を出していく事が必要でした。また、そもそも医療人として、わざわざここに来られた患者様に少しでもよくなって退院してほしい。そのような思いで取り組んで来ました。 当時紹介していただけたのは重症度の高い方や、認知症の方など難しいケースがほとんどでした。しかし、チームで協力して乗り越え、結果として現在まで受け継がれるノウハウが培われました。重度者や認知症に対する対応はいずれの職種も秀でていると思っています。 ―現在でこそ定着しているチームアプローチですが、そこにいたるまでの背景はどのようなものだったのでしょうか? 施設基準としてではなく、密にリハビリを実施しようとすればそれ相応にマンパワーは必要となります。当時は人手が少ないなか、みんなでなんとかやっていました。セラピストがおむつ交換や排せつ介助に入るなどもしていました。みんなで様々な苦労を乗り越えて来たことは、現在のチームアプローチの始まりだったと思います。 その頃、ある来客から「This is none of my business.(これは私の仕事ではありません)」という言葉を紹介してもらいました。例えば受付のスタッフが病棟を歩いていた時に患者さんから「●●してほしい」と声を掛けられた時に、「それは私の仕事ではありません」と断るのではなく、できる限り対応する、もしくは対応できるスタッフに伝達して要望に可能な限り応えるようにすることも大切であるという意味でかけられた言葉(皮肉)でした。 病院のような専門職集団では、つい自分の仕事の領域をつくりがちになります。しかしこの言葉もきっかけにチームで対応する精神が大切であると思うようになり、今でも学卒新人向けの院内研修などで必ず紹介するようにしています。 心がけという意味では、挨拶もその一つです。一人一人が職員として意識を持って顔を上げて挨拶することを、その当時から徹底しました。現在でも来客の方にお褒めいただくことが多く、誇らしく思っています。 ―特にカンファレンスなど医師がほぼ100%参加し、チームアプローチの象徴と思っています。当時からそのような雰囲気だったのでしょうか? 最近でこそ、カンファレンスにほぼ100%医師が参加していますが、はじめからそうだった訳ではありません。 カンファレンスは普段の患者の状態や様子、治療やリハビリの進捗、状態などを共有し、その後の目標や計画を検討する場ですが、回復期リハビリ病棟へ転換した当初は「他の仕事(検査など)があるので」などを理由に医師の参加は非常に悪かったです。基本的には意識の問題で、私自身もそこまで意識して参加できていませんでした。 しかし、ある家族から「なぜここに主治医がいないの?」と言われたことがありました。今思えば、カンファレンスに対する自分の意識を変える最初のきっかけだったかもしれません。医師の基本的な認識としては「医療は治療をするもの」という認識があったこと、そもそも回復期リハビリへの理解が乏しかったことも参加の悪さの背景にはあったと思います。 常々思うのは「理念なきリハビリに未来はない」ということ。当院での理念は「自立支援」に尽きます。この理念を真のものにするためには、より生活に踏み込んだ関わりが必要です。カンファレンスへの医師の参加は必須と考え、15年ほど前に業務命令でカンファレンスを実施する夕方に救急対応以外の医療行為は入れないというスケジュール管理を徹底しました。それから医師の参加は定着し、現在では100%参加することはもちろん、医師がカンファレンスの司会をしています。 ―近年、回復期リハビリ病棟は量的には整備されつつあり、今は「量」から「質」へと重点はシフトしてきている。 2008年に診療報酬で「在宅復帰率」が導入されて以降、次々と「質」の評価が取り入れられました。2016年に導入された実績指標(FIM)は素晴らしい仕組みですが、それを上げることが目的ではなく、あくまで目的は患者自身の状態が良くなり家族の介護負担が軽減することであることが第一義であって、実績指数を達成することが目的ではありません。 客観性を持って評価することが大切であり、実績指標は浸透して然るべきです。目的を間違えないようにしなくてはいけません。病院スタッフ側もこの指標に振り回されることはあってはならないと思います。 ―最後に、この記事をご覧頂いている方にメッセージがあればお願いします。 一人の医師として、さまざまな医療現場を経験し、常々「医師は患者さん、スタッフに教育してもらっている」と痛感しています。これは個人だけでなく、病院も同様です。様々なご意見やご助言をいただくからこそ、日々向上していけると考えています。 幸いこれまで多くのご指導や、ありがたい評価もいただきながらこれまでやってこれました。全国には志高く、さまざまな取り組みをされている医療・介護現場はたくさん存在しています。そうしたところからも多くを学び、現状に満足せず日々向上を目指して行きたいと思います。 ぜひ、これからも細かな部分から忌憚のないご意見をいただければと思います。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 【Profile】 三橋尚志(みつはしたかし) ■役職等 京都大原記念病院 副院長 京都大原記念病院グループ 医療連携室 室長 一般社団法人 回復期リハビリテーション病棟協会 会長 ■資格等 日本リハビリテーション医学会指導医 日本整形外科学会指導医 日本リウマチ学会指導医