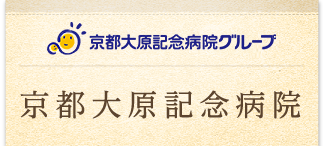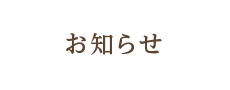リハビリマインド_垣田清人院長 (2/3) 「リハビリは脳を介して取り組むべきだ」
垣田清人医師(京都大原記念病院 院長)に脳神経外科医からリハビリ医療に転身して13年間、見てきたこと、培ったリハビリマインドをテーマに話を伺いました。全3回に分けてご紹介します。 第2回は「リハビリテーション医療についての考え方」がテーマです。2007年4月に院長に着任してから現在までの経験を踏まえて、考えを述べています。 着任当時に感じた医師としての違和感。医師が積極関与する仕組み作りに着手 児玉理事長からの招きで、2007年4月院長に就任しました。「リハビリテーション医ってなんだろう?」と思いながら仕事を始めたことを覚えています。と言うのも、医師によっては治療手技を持つ人もわずかにいましたが、他方セラピスト達の報告を受けて訓練内容を指示するだけの医師もおり、治療手段を持たない医師として違和感があったのです。実際現場に入ってからは、医師がしっかりと関与するような体制が必要と考え、装具検討会設置の他、普段からなるべく訓練室に患者様の様子を見に行く意識付けにも取り組みました。 カンファレンスについては、私が就任する以前から三橋尚志先生を中心に医師の参加が徹底されていました。医師にも、自分の専門領域の報告をするだけでなく、患者様のその後の生活全体を捉え描くための医療外の知識と、それに対応する意識を持つ必要があると思っています。 脳を介したリハビリ、スタッフの成長とともに新たな療法を取り入れる リハビリ医療の世界に入って13年目、基本的なこととして「単に動かす(動かしてもらう)だけではいけない」と考えています。患者様が、脳を介することを意識して取り組まないと意味がないのです。極端な話、例えば患者様が寝ている状態で、スタッフが一生懸命やって関節の可動域を拡げることができても、それはニューロリハビリテーション(脳科学を応用したリハビリテーション)ではないということです。 促通反復療法(通称:川平法)の他、かつてはミラー療法などで器具を作って配ったこともありました。いずれも、脳(への刺激)を介しているので有効と考えてのものでした。「リハビリは脳を介して取り組むべきだ」というのが、私の基本的な考えです。 就任以降、一人一人がしっかりと力を伸ばしてくれて、磁気刺激治療や促通反復療法、LSVT LOUD&BIGなどの新たな療法を取り入れることもできました。最近では、昨年(2018年)京都近衛リハビリテーション病院(以下、近衛)を開設し、体制が一気に拡大しました。スタッフが若返り、院内の状況も変わって来ています。 新しい取り組みは、セラピストのキャリアアップにもつながると思っています。技術を身に付け、次々とスキルアップすることで、やりがいにもなります。得たものは、患者様へのサービス向上だけでなく、経営面でもプラスに働いています。 各スタッフの研究活動や学会発表は、まだまだ増やさないといけません。発表だけでなく、ペーパー(論文等)にまとめて発信することも大切で、院内の総合リハビリテーションセンター前での掲示はその一環です。スタッフにそのような意識で取り組んでもらえるよう、体制をさらに強化していきたいと考えています。 一見弱みの立地も、環境を活かし「大原だからできること」へ 赴任した時から、「この場所で、どこまで頑張れるかな」という不安が、なかったと言えばうそになります。この10年で、京都では回復期リハビリテーション病棟のベッド数が約4倍に増えました。グループとしては、2013年6月の御所南リハビリテーションクリニック(以下、御所南)開設に続き、2018年4月に京都近衛リハビリテーション病院を開設。町中に窓口が増えたことは間違いなくプラスです。人の流れという点でも勉強になっています。とは言え、本院である京都大原記念病院が、大原でしっかりとやっていくことには変わりありません。 幸いにも近年では、「大原だからできること」として「グリーン・ファーム・リハビリテーション®」が徐々に活発になってきています。何度かメディア取材を受け、最近は依頼を受けて学会誌へも寄稿しました。 この取り組みは、患者様が能動的に活動することに意義があります。机上で三角コーンを繰り返し動かす訓練を例に挙げると、基礎練習としての意味はもちろんありますが、「おもしろくないから」と能動的に取り組めない患者様もいます。しかし、退院後の実生活では全て自らの意思で動作をスタートさせなければなりません。能動的な活動を促すために、うまく用いていきたいと考えています。また、併設の老健や特養の日中活動に組み入れるなど、あらゆる形で発展する可能性を感じています。中心的存在である木村彩香医師(指導医)と作業療法士などを起点に、より一層高めてほしいと思います。私としても、この取り組みはきちんと育てて行きたいと考えています。 以前、デイルームでご飯を炊いているというリハビリ病院の話を聞いたことがあります。例えばそのような機会を作り、状態によっては患者様自身に配膳などの役割を持って参加していただくことも、病棟でのリハビリの一環として良いですし、患者様の気分も良くなるだろうと思います。 リハビリ訓練に取り組む時間は、多いとは言え1日3時間です。それ以外の時間を看護師や介護スタッフが工夫してはいるものの、まだまだ寝たりテレビを見たりして過ごす方も多くいます。社会復帰を目指すうえで、実生活に参加を促す機会も大切です。当院の農業(グリーン・ファーム・リハビリテーション®)もリハビリ訓練時間での活用がメインですが、それ以外の活用も広めていけたらと思っています。 【Profile】 垣田清人(かきたきよひと) 京都府立医科大学を卒業後、2年間東京の大学病院で研修した後に帰京。医局へ入らず、京都第一赤十字病院(以下、第一日赤)に直接入職。京都大原記念病院 院長に就任するまでの約30年間在籍。本人曰く「私は外様なんです(笑)」。 |資格| 京都大原記念病院 院長 日本脳神経外科学会専門医 日本脳卒中学会認定脳卒中専門医 【連載第1回はこちら】 変化に富み、忙しくも充実した急性期時代 【連載第3回はこちら】 人生の充実感を探す支援を目指す