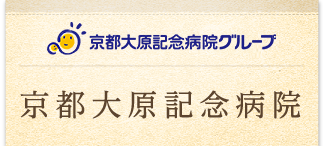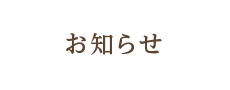身近な物もリハビリ道具に。作業療法のひと工夫を、竹内健二 技師長がご紹介!
京都大原記念病院が担う リハビリテーション は、大きく理学療法(PT)、作業療法(OT)、言語聴覚療法(ST)の3つに分類されます。近年の医学の発展により確立された様々な治療法も、これらの療法と組み合わせて実施しています。 そのなかの一つ作業療法に今日はフィーチャーします。『 作業療法 』とは、一言で言えば、日常生活にある動作を訓練として実施して生活力を取り戻すことを目指す訓練です。主には上肢(肩口から先の手)の動きがメインとなってきます。この訓練は特別な機械を使って実施することもあれば、実はとても誰の身の回りにでも存在するある物を使って訓練することもあります。今日はそんな一面を京都大原記念病院グループ 作業療法士 竹内健二 技師長がご紹介します! そのある物とは『どんぐり』です。そう、あのとなりのトトロで傘を貸した御礼にサツキとメイちゃんがプレゼントされていたどんぐりです。(植える訳ではありません。) 目の前にどんぐりがたくさん入った箱があります。好きなものを一つ選んでテーブルに立ててみましょう。そう声をかけられたらどうするでしょうか? まずは立ちやすそうなどんぐりはどれかな?と探し、一つ決めたら指先でつまんでテーブルに立てますね。この時、ほんの少しだけ角度を変えてみたり、ほんの少し向きを変えてみたり、バランスが取れる重心の位置を探したり、、、無意識に実にデリケートな動作が複雑に行われています。とても細かな指先の動作です。 ごはんを食べる時のお箸使いや、ペットボトルのふたを開けたり、生活で手を使うということは指先のさまざまな細かい動きが連なって成立しています。これはそのための指先の細かな動きを取り戻すための訓練です。このような細かな動作ができるかどうかを『 巧緻性(こうちせい) 』と言います。 次はすこしやり方を変えてみます。どんぐりをつかむことに限らず「手を使う」時、改めて意識してみると手が丸くなっているのは想像がつくでしょうか?(写真①)しかし、これが脳卒中等の中枢神経に影響を及ぼす疾患などを発症すると突っ張るように平たく(写真②)なってしまうことがあります。 [caption id="attachment_806" align="alignnone" width="400"] 写真① ※イメージです。[/caption] [caption id="attachment_812" align="alignnone" width="400"] 写真② ※イメージです。[/caption] 手が平たくつっぱると指先を使った動作は非常に難しくなります(写真③)。こうした状態の時、手をほぐしたりしてから指先の細かな動きを訓練しつつ、手が使いやすい丸い形となるように一連の訓練をどんぐりを使って取り組むこともあります。 [caption id="attachment_801" align="alignnone" width="400"] 写真③ 消しゴムも指先を使います[/caption] どんぐりをテーブルに拡げました。ここからはシンプル。指先(人差し指と親指など)でつかんで(写真④)手のひらへ送る(写真⑤)。 手のひらのどんぐりはしっかりと持ちながら、また新たなものを掴んで手のひらへ送ります。これを繰り返し『もうこれ以上持てない』というところまでがんばります。(あふれてポロっと落ちるくらいに)(写真⑥)。 [caption id="attachment_803" align="alignnone" width="400"] 写真④[/caption] [caption id="attachment_804" align="alignnone" width="400"] 写真⑤[/caption] [caption id="attachment_813" align="alignnone" width="400"] 写真⑥[/caption] その時、自然と手が丸い形になっていると思います。この状態でギュッギュッと握って1セット完了です。 この一連の動きを分解してみますと、 ① 指先でどんぐりをつまみ、つまんだどんぐりを手のひらへ送る ② 手のひらのどんぐりは握りながら(小指や薬指などを使って) ③ どんぐりをつまんで手のひらへ送る ④ 手のひらがいっぱいになったら、丸い形になっていることを意識しながら握る このように分解できます。それぞれに指先の細かな動きが必要になったり、また一定の握力が必要になったり、手の形を適切に形作ったりといろんな訓練要素が存在します。 こんな風に身近にあるどんぐりも時には立派なリハビリテーション訓練用具になったりします。それが作業療法のおもしろいところです。 生活動作というだけあり、患者様の生活スタイルが違えば取り組むべき課題も訓練も人それぞれ大きく変わるため、どんぐりだけでなく、様々な道具を使って取り組むことも多く、アクティビティ要素を持つ訓練プログラムになることもしばしば。当院では、農園で野菜を収穫してもらい、それを調理する訓練などもあります。 さまざまなプログラムを展開するのはそれぞれの生活スタイルに合わせて訓練をするという側面だけでなく、患者さんの意欲を引き出したいという狙いもあります。これからもただ目的を強調してつらい訓練にするのでも、ただ楽しく目的が分かりづらい訓練でもなく、楽しく意欲的に目的を持って取り組んでいただけるようお一人お一人に合わせたリハビリテーションを提供していきたいと考えています。 ※ 訓練に用いるどんぐりは、全て熱殺菌してから使用しています。 |監修| 京都大原記念病院グループリハビリテーション部 作業療法士 技師長 竹内健二