読売新聞に副院長 三橋尚志 医師のコメントが掲載されました!
10月20日(水)の読売新聞朝刊の「病院の実力 ― 生活復帰へ 回復期リハビリ ―」に、当院副院長の三橋尚志医師のコメントが掲載されました。ぜひご覧ください。 <画像をクリックすると、記事をご覧いただけます。> 三橋尚志のインタビュー記事をこちらからもご覧いただけます。 【「医療連携室」の活動から見えてくるもの】 【回復期リハビリテーション病棟協会 会長 就任への想い】
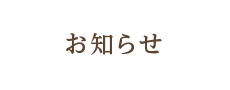
10月20日(水)の読売新聞朝刊の「病院の実力 ― 生活復帰へ 回復期リハビリ ―」に、当院副院長の三橋尚志医師のコメントが掲載されました。ぜひご覧ください。 <画像をクリックすると、記事をご覧いただけます。> 三橋尚志のインタビュー記事をこちらからもご覧いただけます。 【「医療連携室」の活動から見えてくるもの】 【回復期リハビリテーション病棟協会 会長 就任への想い】
当院では、入院患者様の利便性向上を目的に「無線ネットワーク(Wi-Fi)」を利用できる環境を整備いたしました。ご利用を希望される方は以下の注意事項に遵守いただきお手持ちの機器(パソコン、タブレット、スマートフォン等)からご利用ください。 ご利用可能時間 いつでもご利用できます。 ご利用可能エリア 各病棟デイルーム 各病室内 ※院内にもポスターを掲示しております。 ※混雑等により、エリア内においても接続が不安定になることがあります。 ご利用方法 ご利用希望者は病棟または受付まで申し出ください。 SSIDおよびパスワードをお渡しします。接続設定を端末にて各自設定いただき、ご利用ください。 注意事項 ●利用を希望される方は別紙「京都大原記念病院公衆無線ネットワーク(Wi-Fi)規約」に同意のうえ、ご自身での責任においてご利用ください。 ●Wi-Fiの利用に関する関連機器の貸し出しは行っておりません。 ●当院では接続や設定方法など利用に関する「質問受付」及び「個別サポート」等の対応は致しかねます。予めご了承ください。 ●他の利用者の迷惑にならないようマナーを守りご利用ください。 ●パソコン、タブレット、スマートフォン、他各種ゲーム機器等への接続および動作は保証できませんのでご了承ください。 ●ご利用に際してのウィルス対策やセキュリティ設定等はご自身の責任にてお願いします。 ●サービスのご利用により発生した損失・損害につきましては当院では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●医療行為での影響がある場合、病院職員から利用中止をお願いする場合がございます。 京都大原記念病院
7月のある日の昼食。ジャガイモの冷製スープ“ビシソワーズ”をお出ししました。この一杯には、実はいろんな想いがこめられています。 [caption id="attachment_1078" align="alignnone" width="300"] ジャガイモの冷製スープ「ビシソワーズ」[/caption] 主な材料の“ジャガイモ”は畑で獲れたもの。ただ単に畑で獲れたのではなく、グリーン・ファーム・リハビリテーションⓇの活動で患者様に収穫していただいたものです。この意味を、私たちは大切にしたいと思っています。 [caption id="attachment_1080" align="alignnone" width="300"] ジャガイモを収穫された患者様(中央)と、看護師(右)とセラピスト(左)[/caption] この活動を病院という一つの社会で取り組む「社会活動」と捉えると、その成果が誰かのもとに届く瞬間には、とても意味があると思うのです。私たちが常に大切にするのは、「退院後の生活ができる限りその人らしいものであるように」という想い。畑の野菜は形や大きさが不揃いで、調理がちょっと難しいこともあります。でも、この活動の持つ意味を共有してチームで準備を進めました。 [caption id="attachment_1083" align="alignnone" width="300"] 収穫したジャガイモの皮むきも作業療法に[/caption] 収穫してから提供するまでの期間、ポスターや収穫物をディスプレイ展示するなどして、私たちが大切にしたいこの活動の意味をお伝えしてきました。少し届いたのか、患者様からは「いつもよりも食欲が出る!」という嬉しい感想が聞かれました。準備に関わったスタッフにとっては本当に励みになるお声でした。 [caption id="attachment_1082" align="alignnone" width="300"] 準備の様子に興味を持ってくださる患者様も。[/caption] 今回は職員食堂でも同じスープを用意し、アンケートを実施しました。畑の活動に参加したことがなかった職員からも、「(活動風景のポスターを見て)患者様も職員も良い笑顔だったのが良かった」「活動の目指すところが分かった!」「患者様や同僚とも畑の話をしてみようと思う」などの声が聞かれました。また少し、活動の輪が広がりました。 [caption id="attachment_1079" align="alignnone" width="300"] 「いつもより食欲が出る!」と管理栄養士(右)に感想を聞かせてくださいました。[/caption] 今年度は毎月、お食事として提供できる見通しになりました。次は、キュウリやトマトです。活動に込める想いを大切に、患者様と、職員が心の通うみんなの活動として高めていきたいと思います。
京都大原記念病院グループ(以下、グループ)では、リハビリテーション病院を中心に、医療・介護サービスのネットワークの面展開で、丁寧できめ細やかなサービスの提供に努めています。そのなかで、患者様を中心に様々な人をつなぐ役割を担う「医療連携室」の活動を通じて見えてくるものを、室長の三橋尚志医師と、副室長の児玉直俊医師に聞きしました。<本記事は京都大原記念病院グループ広報誌「orinas( vol.2/2021.04)」の掲載記事です> ――はじめに、お二人が室長・副室長を務められている「医療連携室」とは何かを教えてください。 三橋尚志医師(以下、三橋)>我々の病院は地域医療の「回復期」というステージを担っています。病状が不安定で緊急性を要する期間(急性期)で治療を終えた患者様が、自宅や社会に戻ってからの生活を少しでもその人らしい状態にするための「リハビリテーション(以下、リハビリ)」を専門としています。 そのなかで「医療連携室」が担う地域連携には2つの役割があります。一つ目は、リハビリを目的とした患者様を受け入れるための急性期病院等との「前方連携」、二つ目は、患者様がご自宅や社会へスムーズに戻れるよう退院支援を行う「後方連携」です。 児玉直俊医師(以下、児玉)>「医療連携室」は、「京都大原記念病院」と「京都近衛リハビリテーション病院(以下、京都近衛リハ病院)」の2拠点で、三橋先生、私の医師2人を含め、看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)、事務職の総勢19名で活動しています。直接的な支援は相談援助職の医療ソーシャルワーカーがメインに担います。看護師に加えて、3年前から理学療法士が入院時に関わるのも特長です。 ――<回復期リハビリ病院>として、大原の環境は活かされているのでしょうか。 三橋>大原の自然環境を最大限活かしてきたら、<回復期リハビリ病院>としての成長につながったという感じですね。四季の風景、草花の香りは良い刺激になります。 児玉>患者様は約3,4か月、過ごされますが、病室や訓練室だけだと時間が止まっているように感じる方もいらっしゃいます。自然からの刺激は魅力だと思いますね。入院されている患者様同士の関係性もかなり強いですよね。 三橋>ある意味特異な立地のため、他にできないコトをやろうと挑戦しつづけ、様々な技術を積極的に取り入れて「病院の魅力づくり」を行ってきたのが、良かったと思います。多機能な回復期リハビリ病院として、訓練の場、生活の場をより良くしようと工夫を重ねてきたことが強みになっていますね。最近の「グリーン・ファーム・リハビリテーション(R)」もまさにそれにあたります。 児玉>とはいえ昔は、患者様の紹介を得るのが大変だったと聞きますが… 三橋>昔は、リハビリそのものの理解も進んでいませんでした。今なら当たり前のようにリハビリが必要と判断される患者様も、当時は積極的に取り組む機会を得られなかった、ということもしばしばでした。 グループ代表からは「私たちが何をしているかを知ってもらうためには、汗をかかないといけないだろうな」と常々言われていました。 [caption id="attachment_1071" align="alignnone" width="600"] 2021年3月25日京都大原児玉山荘(京都大原記念病院敷地内)にて[/caption] ――いろんな苦労があったでしょうね。 三橋>そうですね。対応に悩む重度のケースも、多職種チームで数多く乗り越えて来ました。結果として、現在も重度の方や認知症の方への対応はどの職種も秀でていると思っています。 また、急性期病院の人たちが予想もしないような良い結果を、うちの多職種のチームが次々出し続けてきたのが素晴らしかった。 ――予想もつかないような結果、ですか。 三橋>急性期病院の先生方が「もう歩けないだろう」と思っていた患者様が、笑顔で歩けるようになられたり。「もう口から食べられないだろう」と思っていた患者様が、食べられるようになった。一つひとつ、取り組みを積み重ねてきたことで理解が広がってきました。 児玉>長年の実践で築かれた信頼ということですよね。 三橋>そうですね。スタッフ力の賜物というか……。当初は、スタッフみんな本当に大変だったと思います。だからこそ、今でも受け継がれているのが誇らしいですね。 先日、ご家族がずっと付き添わなければならないほど認知症が進み、毎晩とても大変だったという方を受け入れましたが…うちに来られたら、その日の晩から穏やかになられました。 ――その晩から、ですか。 三橋>回復期リハビリ病棟が制度化される前から実践で培ってきた対応力があるのだと思います。児玉先生がおられる「京都近衛リハビリテーション病院(以下、京都近衛リハ病院)」にも、受け継がれているのではないですか? 児玉>はい、確かにそうですね。「京都大原記念病院」で鍛えられたスタッフが「京都近衛リハ病院」の立ち上げメンバーとして、新しいスタッフを巻き込んで、チームづくりをしてくれています。 ――2018年に「京都近衛リハ病院」ができて3年経ちました。街中の大通り沿いにあることもあり、色々な急性期病院や、一般の患者様からいろんな期待も受けられると思いますが、どんな感じですか? 児玉>そもそも世の中的に、急性期病院に入院期間短縮が求められていることを受けて、より早い段階で受け入れる拠点となるために開院されました。そんな背景もあってか、癌治療中であるとか、心臓にトラブルを抱えているとか、これまで以上に全身管理が必要な方が多いです。私はもともと「循環器」が専門ですから、その知識も活かせています。 ――何か工夫されていることはありますか? 児玉>大原でもそうですが急性期病院と連携して診るケースが増加しています。大学病院の専門チームに診てもらうとか、外来受診と連携するとか、そういう形で受け入れることができています。しかし、その分、個別の対応が必要です。スタッフの皆さんの対応力には、本当に頭が下がる思いです。 ――長年、患者様のリハビリの方針を検討する月1回のカンファレンスに、ご家族にも参加いただくことが定着していますよね。 三橋>20年ほど前から徹底しています。患者様本人とご家族が参加することでスムーズに理解が得られ、カンファレンスの意義もあがります。会は医師が話を仕切りますが、開催するまではお任せなので(笑)動いてくれるスタッフがすごいと思います。 児玉>やっぱり、スタッフのチカラは大きいですね。個々のスタッフの対応をみていると、一人ひとりの患者様の人生に向き合い「支える」ことが、一番大切だと思います。 三橋>「支える」ですね。まずはその人ができることを伸ばすためのリハビリに取り組むべき(リハビリ前置主義)というのが<回復期リハビリ病院>の重要な考え方です。「してあげる」と混同して、介護保険サービスに頼る前提の支援を行うと、かえってその人らしさを奪いかねませんからね。 住み慣れた場所でその人らしく暮らせる地域づくり(地域包括ケアシステム)のためにも、その視点が大切です。その意味ではリンクする考え方だと思っています。 我々が最終的に目指すのは、地域への貢献です。患者様、一人ひとりとミクロに接していくと、地域の全体像やマクロの問題が見えてきます。一人ひとりの患者様に人として向き合うことが、より良い地域づくりに繋がると思います。患者様一人ひとりとの顔の見える関係づくりを、これからも大切にしていきたいですね。 児玉>医療連携室としても、私たち(医師)がグループの介護サービスにも踏み込んで関わる体制ができつつありますから、医療、介護の「面」で支えるという意味でも築き上げたいです。スタッフと共に医療と介護の両輪をまわしていきたいですね。 グループが築き上げてきた経験や信頼関係は大きな財産。患者様の退院後の生活がより豊かでその人らしいものになってほしいとの思いを大切に、これからも頑張りたいと思います。
京都府作業療法士会の「事例検討会」で、小森奈々療法士、松岡ちさと療法士が「優秀賞」を受賞。代表で小森療法士(京都大原記念病院)に話を聞きました。 「70代の専業主婦、脳梗塞後の高次脳機能障害により、段取り良く活動したり、身の回りに注意を払いづらくなった患者様に、ビデオを使った動作の振り返りや、メモで事前に段取りを確認するなど気づきを提供し、改善につながった事例を報告しました。」今回の受賞に「今回の受賞をとてもうれしく思います。これを励みに、これからも頑張っていきたいと思います。」と抱負を聞かせてくれました。
3月1日から看護介護部が京都大原記念病院、京都近衛リハビリテーション病院内で「研究発表(ポスター)」を実施しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、2020年からグループ研究大会の開催を自粛していることをきっかけとした初めての試みです。 今回は「事例報告」「職員の意識変化」「業務改善」などをテーマとした6演題が発表されました。日々の気づきから学ぶうえで、体系的にまとめて発信することは大切な機会となります。看護・介護の質向上を目指し、今後も様々に工夫を凝らして取り組んでいきます。 ■各発表は演題名をクリックするとご覧いただけます 演題1≫ 身体拘束のミトン解除へ ~抑制解除に向けた代替策~ 演題2≫ 家屋調査に対する認識や視点についてアンケート調査を実施して 演題3≫ 患者様の身だしなみ・環境調整に対する取り組み ~スタッフの意識の変化~ 演題4≫ 居残り業務の見直し 〜時間外勤務の短縮〜 演題5≫ 転倒防止対策 ~情報提供用紙「安心シート」による効果~ 演題6≫ 回復期リハ病棟で働く介護職員の意識の変化 ~カンファレンスに参加して~
京都大原記念病院グループと京都第一赤十字病院(以下・第一日赤)との症例報告会が2月9日、第一日赤とグループ拠点施設を結びWeb形式で開かれ、患者2人の症例について話し合った。梅澤邦彦・第一日赤脳神経外科部長が座長を務めた。 ■1例目 「胃瘻造設が転機となった脳梗塞後の男性例~自力経口摂取に向けた取り組み」 脳血管障害の回復過程で胃瘻を造設した60代男性患者について、食事を経口摂取できるようになるまでの各職種の取り組みについて報告した。 ■2例目 「左側脳室三角部腫瘍術後で高次脳機能障害を呈した症例~復職を目指して」 看護師としての復職を目指す30代女性患者について、体力向上や計算や書類記載のスピードアップなどの取り組みにより復職を果たすまでの経過を報告した。 第一日赤側からは手術などの急性期治療を行った患者が経口摂取や復職を果たしたことについて、主治医や担当セラピストから「大変うれしく思う」などの感想が寄せられた。梅澤部長からも後日、経口摂取のためにあらゆる可能性を模索する姿勢にお褒めのコメントが届いた。 会は、発症後の急性期の治療に当たる第一日赤と、その後のリハビリを担う同グループ(京都大原記念病院、京都近衛リハビリテーション病院、御所南リハビリテーションクリニック)が、共通して診た患者の回復の度合いについて理解を深める狙いで年1回開いている。 新型コロナウイルス感染防止のため第一日赤とは初めてのWeb開催となったが、垣田清人・京都大原記念病院院長と今井啓輔・第一日赤脳神経・脳卒中科部長からはともに「コロナ後に向けてさらなる協力関係を築いていきたい」とのあいさつがあった。 [caption id="attachment_503" align="alignnone" width="300"] 垣田清人 院長(京都大原記念病院)[/caption]
各種報道等にて、新型コロナウイルス感染症の拡大による「医療の逼迫」が起こり、同感染症の治療はおろか通常の医療提供にも支障をきたしつつある状況はご存知かと思います。 こうした状況を考慮し、「回復期」を担う京都大原記念病院では、同感染症の治療を終え、リハビリテーションを必要とされる患者様を受け入れいたします。 患者様、ご家族をはじめ関係の皆様におかれましては、本方針にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 令和3年2月15日 京都大原記念病院 院長 垣田清人
診療実績ページを「数字でわかる京都大原記念病院」としてリニューアルしました。 リハビリテーションに求められる役割が年々増しています。一層、質・量双方の充実が求められるなか、当院としても客観的な評価に基づき取り組みの改善につなげていくこと、また当院について「数字」で具体的にご理解いただくことを目的に公開しています。 これまでより、公開範囲を広げる形でリニューアルしております。ご興味がございましたらご覧ください。 詳しくはこちら
1月15日(金)京都新聞・夕刊一面に、2020年11月に当グループと、京都府立医科大学、タキイ種苗が締結した「グリーン・ファーム・リハビリテーション®に関する連携協定書」についての話題が掲載されました。取り組みについての紹介や、関係者のコメントなどもご紹介いただいております。ぜひご覧ください。(記事掲載について「京都新聞社」の許諾済み)