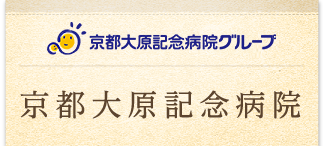【特別対談】「医療連携室」の活動から見えてくるもの
京都大原記念病院グループ(以下、グループ)では、リハビリテーション病院を中心に、医療・介護サービスのネットワークの面展開で、丁寧できめ細やかなサービスの提供に努めています。そのなかで、患者様を中心に様々な人をつなぐ役割を担う「医療連携室」の活動を通じて見えてくるものを、室長の三橋尚志医師と、副室長の児玉直俊医師に聞きしました。<本記事は京都大原記念病院グループ広報誌「orinas( vol.2/2021.04)」の掲載記事です>

――はじめに、お二人が室長・副室長を務められている「医療連携室」とは何かを教えてください。
三橋尚志医師(以下、三橋)>我々の病院は地域医療の「回復期」というステージを担っています。病状が不安定で緊急性を要する期間(急性期)で治療を終えた患者様が、自宅や社会に戻ってからの生活を少しでもその人らしい状態にするための「リハビリテーション(以下、リハビリ)」を専門としています。
そのなかで「医療連携室」が担う地域連携には2つの役割があります。一つ目は、リハビリを目的とした患者様を受け入れるための急性期病院等との「前方連携」、二つ目は、患者様がご自宅や社会へスムーズに戻れるよう退院支援を行う「後方連携」です。
児玉直俊医師(以下、児玉)>「医療連携室」は、「京都大原記念病院」と「京都近衛リハビリテーション病院(以下、京都近衛リハ病院)」の2拠点で、三橋先生、私の医師2人を含め、看護師、理学療法士、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)、事務職の総勢19名で活動しています。直接的な支援は相談援助職の医療ソーシャルワーカーがメインに担います。看護師に加えて、3年前から理学療法士が入院時に関わるのも特長です。
――<回復期リハビリ病院>として、大原の環境は活かされているのでしょうか。
三橋>大原の自然環境を最大限活かしてきたら、<回復期リハビリ病院>としての成長につながったという感じですね。四季の風景、草花の香りは良い刺激になります。
児玉>患者様は約3,4か月、過ごされますが、病室や訓練室だけだと時間が止まっているように感じる方もいらっしゃいます。自然からの刺激は魅力だと思いますね。入院されている患者様同士の関係性もかなり強いですよね。
三橋>ある意味特異な立地のため、他にできないコトをやろうと挑戦しつづけ、様々な技術を積極的に取り入れて「病院の魅力づくり」を行ってきたのが、良かったと思います。多機能な回復期リハビリ病院として、訓練の場、生活の場をより良くしようと工夫を重ねてきたことが強みになっていますね。最近の「グリーン・ファーム・リハビリテーション(R)」もまさにそれにあたります。

児玉>とはいえ昔は、患者様の紹介を得るのが大変だったと聞きますが…
三橋>昔は、リハビリそのものの理解も進んでいませんでした。今なら当たり前のようにリハビリが必要と判断される患者様も、当時は積極的に取り組む機会を得られなかった、ということもしばしばでした。
グループ代表からは「私たちが何をしているかを知ってもらうためには、汗をかかないといけないだろうな」と常々言われていました。

2021年3月25日京都大原児玉山荘(京都大原記念病院敷地内)にて
――いろんな苦労があったでしょうね。
三橋>そうですね。対応に悩む重度のケースも、多職種チームで数多く乗り越えて来ました。結果として、現在も重度の方や認知症の方への対応はどの職種も秀でていると思っています。
また、急性期病院の人たちが予想もしないような良い結果を、うちの多職種のチームが次々出し続けてきたのが素晴らしかった。
――予想もつかないような結果、ですか。
三橋>急性期病院の先生方が「もう歩けないだろう」と思っていた患者様が、笑顔で歩けるようになられたり。「もう口から食べられないだろう」と思っていた患者様が、食べられるようになった。一つひとつ、取り組みを積み重ねてきたことで理解が広がってきました。
児玉>長年の実践で築かれた信頼ということですよね。
三橋>そうですね。スタッフ力の賜物というか……。当初は、スタッフみんな本当に大変だったと思います。だからこそ、今でも受け継がれているのが誇らしいですね。
先日、ご家族がずっと付き添わなければならないほど認知症が進み、毎晩とても大変だったという方を受け入れましたが…うちに来られたら、その日の晩から穏やかになられました。
――その晩から、ですか。
三橋>回復期リハビリ病棟が制度化される前から実践で培ってきた対応力があるのだと思います。児玉先生がおられる「京都近衛リハビリテーション病院(以下、京都近衛リハ病院)」にも、受け継がれているのではないですか?
児玉>はい、確かにそうですね。「京都大原記念病院」で鍛えられたスタッフが「京都近衛リハ病院」の立ち上げメンバーとして、新しいスタッフを巻き込んで、チームづくりをしてくれています。
――2018年に「京都近衛リハ病院」ができて3年経ちました。街中の大通り沿いにあることもあり、色々な急性期病院や、一般の患者様からいろんな期待も受けられると思いますが、どんな感じですか?
児玉>そもそも世の中的に、急性期病院に入院期間短縮が求められていることを受けて、より早い段階で受け入れる拠点となるために開院されました。そんな背景もあってか、癌治療中であるとか、心臓にトラブルを抱えているとか、これまで以上に全身管理が必要な方が多いです。私はもともと「循環器」が専門ですから、その知識も活かせています。
-1024x683.jpg)
――何か工夫されていることはありますか?
児玉>大原でもそうですが急性期病院と連携して診るケースが増加しています。大学病院の専門チームに診てもらうとか、外来受診と連携するとか、そういう形で受け入れることができています。しかし、その分、個別の対応が必要です。スタッフの皆さんの対応力には、本当に頭が下がる思いです。
――長年、患者様のリハビリの方針を検討する月1回のカンファレンスに、ご家族にも参加いただくことが定着していますよね。
三橋>20年ほど前から徹底しています。患者様本人とご家族が参加することでスムーズに理解が得られ、カンファレンスの意義もあがります。会は医師が話を仕切りますが、開催するまではお任せなので(笑)動いてくれるスタッフがすごいと思います。
児玉>やっぱり、スタッフのチカラは大きいですね。個々のスタッフの対応をみていると、一人ひとりの患者様の人生に向き合い「支える」ことが、一番大切だと思います。
三橋>「支える」ですね。まずはその人ができることを伸ばすためのリハビリに取り組むべき(リハビリ前置主義)というのが<回復期リハビリ病院>の重要な考え方です。「してあげる」と混同して、介護保険サービスに頼る前提の支援を行うと、かえってその人らしさを奪いかねませんからね。
-1024x683.jpg)
住み慣れた場所でその人らしく暮らせる地域づくり(地域包括ケアシステム)のためにも、その視点が大切です。その意味ではリンクする考え方だと思っています。
我々が最終的に目指すのは、地域への貢献です。患者様、一人ひとりとミクロに接していくと、地域の全体像やマクロの問題が見えてきます。一人ひとりの患者様に人として向き合うことが、より良い地域づくりに繋がると思います。患者様一人ひとりとの顔の見える関係づくりを、これからも大切にしていきたいですね。
児玉>医療連携室としても、私たち(医師)がグループの介護サービスにも踏み込んで関わる体制ができつつありますから、医療、介護の「面」で支えるという意味でも築き上げたいです。スタッフと共に医療と介護の両輪をまわしていきたいですね。
グループが築き上げてきた経験や信頼関係は大きな財産。患者様の退院後の生活がより豊かでその人らしいものになってほしいとの思いを大切に、これからも頑張りたいと思います。

関連記事
- 2025年10月01日
- 訪問リハビリテーション事業所の移設について
- 2025年09月03日
- 職員満足度調査を実施しました
- 2025年07月26日
- 本質的な強みはどこに?|京都大原記念病院 「見えラボ」 進行中