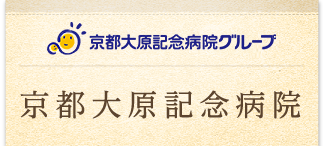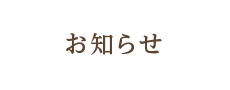京都府立医科大学とのリハビリテーション症例報告会を開催
京都大原記念病院と京都府立医科大学のリハビリテーション症例報告会が7月25日、京都市上京区の同大学で開かれ、双方の医師やリハビリ療法士、看護師ら約60人が集い、報告のあった2症例についてリハビリの方法や効果について理解を深めた。 症例報告会は、発症後の急性期医療を行った同大学に向けて、その後の回復期リハビリテーションを担った同病院が、患者転院後にどういった経過を辿ったかを報告。今後の治療の参考にするとともに、双方の信頼関係の維持発展を目標に、この時期に毎年開いている。同大学神経内科学の水野敏樹教授が司会を務め、垣田清人・同病院院長が開会あいさつを行った。 一例目は「当院におけるパーキンソン病に対するリハビリテーション~H&YⅢへのアプローチ~」と題して京都大原記念病院の北川知安紀・理学療法士が、パーキンソン病に効果のあるLSVTⓇを実施して改善を認めた症例について報告した。 二例目は「脳卒中患者の介助量軽減に向けた取り組み~家族の協力と多彩なリハメニューを通じて」と題して古谷典久看護師が報告した。患者は90代後半の女性。畑仕事に長年携わってきたことから、同病院が行う農作業を取り入れたグリーン・ファーム・リハビリテーション®が効果を上げた実例だった。 詳しくは広報誌「 和音9月号(発行・掲載:9月1日予定) 」でも特集予定です。 ご興味のある方はこちら(グループサイトへリンクします)も合せてご覧ください。