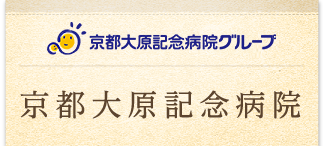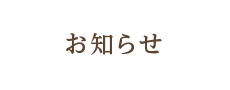【グループ研究大会の表彰演題をご紹介】回復期リハビリテーション病棟患者の栄養状態について
近年、回復期リハビリテーション病棟には低栄養の方が多いことが明らかになっています。低栄養は身体機能・気力の低下・疲労などがみられるためリハビリの効果が上がりにくく、リハビリと同時に栄養改善していくことが重要であると言われています。先行研究では医療チームの一員として管理栄養士が介入することで栄養改善や効率的なリハビリへとつながることが報告されており、当院でも2018年4月より各リハビリテーション病棟に管理栄養士を1名配置し、多職種と共に栄養管理を行っています。 今回栄養科では効果的なリハビリにつながる栄養管理の足掛かりとするために実態調査を行いました。対象は当院の回復期リハビリテーション病棟の入院患者の86%を占める65歳以上の患者としました。結果は入院時には、「BMI18.5未満(低体重)」が26%、「Alb3.2g/dl以下(重度-中等度低値)」が23%で、「MNA®-SF※1 低栄養」が68%と低栄養状態の方が多く、特に「経口摂取を目指す方」や「食事形態のアップを目指す方」が低栄養であることがわかりました。また、「入院時と退院時の栄養状態の変化」については、必要エネルギー量と摂取エネルギー量、エネルギー充足率(摂取エネルギー量/必要エネルギー量)、MNA®-SFで有意な改善がみられ、食事形態も全体的にアップしており、入院時よりも退院時に栄養状態は改善していました。さらにMNA®-SFの変化とFIM※2との関係をみると、栄養改善するほどFIM利得は高いことがわかりました。 1日最大3時間のリハビリを行う回復期リハ病棟は、急性期病院や施設・在宅での生活よりも必要エネルギー量が増加します。リハビリを進めていく中で、活動量の変化・食事量・体重変化は栄養管理をする上で重要な情報です。特に、低栄養状態の方や、経口摂取を目指す方・食事形態アップを目指す方については、密に多職種連携を図り、先手の栄養サポートが可能となれば体重減少や重度の低栄養に陥るリスクを回避できると考えます。多職種に協力を得ながら情報収集し、私達、管理栄養士からも評価ごとの栄養状態の発信をしていきたいと思います。そして『管理栄養士』は栄養で食べ物を表現できる唯一の職種でもあります。リハビリをする上でどのように食事・栄養を摂ってもらうかは日々悩むこともありますが、患者様一人ひとりのニーズをキャッチし、患者様にしっかりと食べて頂き栄養改善や効果的なリハビリへとつながるよう、食事サービスと栄養管理を合わせて今後も取り組んでいきます。 京都大原記念病院 管理栄養士 古谷香梨 ※1 MNA®-SF: Mini Nutritional Assessment-Short Formの略で、簡易栄養状態評価表のこと。65歳以上の高齢者の栄養状態を簡単に評価するためのツールである。 ※2 FIM:Functional Independence Measureの略で、機能的自立度評価法のこと。ADL(日常生活動作)を評価するツール。食事、排泄、移動などの運動項目(13項目)と、コミュニケーションなどの認知項目(5項目)から構成され、1~7点の点数で採点、合計する。