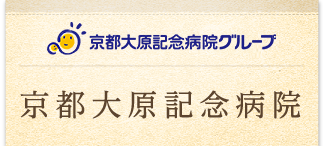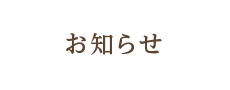2月4日から2日間、京都産業会館を会場に第8回京都リハビリテーション医学会学術大会が開催されました。会には、京都大原記念病院グループの医師、セラピストらを含む、京都のリハビリ医療に関わる延べ約300名が一同に会しました。
真の多職種連携へ
本大会には「Road to true interdisciplinary bonds-真の多職種連携・絆への道しるべ-」がテーマに掲げられました。脳卒中等を発症した時、救命を第一にできる限り早く離床を目指す急性期、状態が落ち着いた後、社会復帰を目指して集中的にリハビリに取り組む回復期、生活の場を在宅へと移し生活の質(QOL)向上を目指す生活期へとバトンが託されます。肝となるのが「多職種連携」です。病院内はもちろん、在宅等にステージが移れば異なる医療・介護サービス事業所間での連携も必要となります。入院期間が決まっている急性期、回復期と異なり、その先に生活期が何十年も続くことを理解して、各専門的視点から患者様・ご家族の想いを支援していくことが重要です。本大会はその視点から、地域における職種間の連携の在り方についてさまざまな議論が交わされました。
次のステージへ
リハビリ医学の研究、教育の普及を目的に立ち上がった本会は10周年を迎えました。節目を機に発展的に次のステージへ歩みを進めることが理事会から報告されました。時代は移り変わり、医師を中心とした教育活動としての役割は果たすことができた。医学、医療だけでなく介護、福祉の充実を図るとともに、横串を指して地域のインフラとなっていくことを目指す場へと生まれ変わります。
京都大原記念病院グループは引き続き、京都のリハビリ医療の発展に向けて活動するとともに、社会の要請に応える地域の暮らしの安心のあり方を考えていきます。
京都大原記念病院グループ関連演題等
教育講演|回復期リハビリテーション病棟の現状とこれから
演者|三橋尚志(回復期リハビリテーション病棟協会会長/京都大原記念病院副院長)
座長|武澤信夫(御所南リハビリテーションクリニック)
[caption id="attachment_1216" align="alignnone" width="150"] 三橋尚志医師[/caption]
[caption id="attachment_1215" align="alignnone" width="150"] 武澤信夫医師[/caption]
特別企画|回復期と生活期連携
演者|増田剛(京都大原記念病院グループ リハビリテーション部 課長 作業療法士)
特別企画|各職種からの提言
演者|児玉直俊(京都近衛リハビリテーション病院 院長)
パネルディスカッション|医師同士の連携
演者|児玉万実(御所南リハビリテーションクリニック 院長)
[caption id="attachment_1235" align="alignnone" width="200"] 写真左から1人目 児玉万実医師[/caption]
一般演題|ポスターセッション
演題|亜急性期脳卒中患者の重度上肢機能障害に対しての反復性経頭蓋磁気刺激の検討
演者|大道卓摩(京都大原記念病院 医師)
一般演題|ポスターセッション
演題|コロナ禍における脳卒中片麻痺患者の独居生活への復帰に向けた取り組み
演者|加藤慎也(京都近衛リハビリテーション病院 理学療法士)
続きを見る