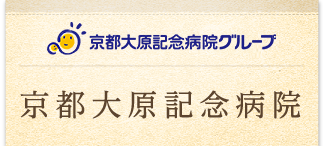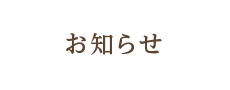リハビリテーション公開講座in京都大原 開催しました(1)
11月23日(祝・木)、リハビリテーション公開講座in京都大原を京都大原記念病院 地域交流スペースを中心に、初めて大原で開催しました。約420人の来場者は3人の医師の講演とともに、おおはら秋の健康まつりとして健康チェックなど施設内に設けられたコーナーを巡り、錦秋の大原の一日を楽しみました。 午前・午後の2部制で開催された、全4講演について、今回を含めて全4回で今後ご紹介していきます。本日は第1講演となった、元患者 浅井努氏の講演です。 午前の部ではまず元患者で八幡高教諭の浅井努さん(48)が「脳梗塞なんかに負けてたまるか~大原でのリハビリ奮闘75日」と題して基調報告。浅井さんはレスリング部の監督を務め、毎日ランニングとスパーリングを行っていたが、昨年10月24日夜、入浴しようとして立ち上がった時に左へ崩れ落ちた。めまいと吐き気があり、救急車で運ばれ検査を受けたところ、首の延髄の脳梗塞であるワレンベルク症候群と診察されました。 左半身が動かず「何で俺がこんな病気に」と落ち込んだが激務と飲酒、長時間のサウナといった生活習慣を反省し、京都大原記念病院への転院を機に、「昨日より一歩前に出よう」と片足立ちの時間やスクワットの回数を増やしていきました。「ストイックに自分を追い込み五輪を目指した時代を思い出した」といい、今はスパーリングこそしないものの、生徒の指導にも復帰したが、早く帰るよう心掛け、酒は一滴も飲まず、新たな趣味の自転車に取り組んでいます。 リハビリテーション公開講座in京都大原 開催しました(2)についてはこちら リハビリテーション公開講座in京都大原 開催しました(3)についてはこちら リハビリテーション公開講座in京都大原 開催しました(4)についてはこちら 本講座は52社の協賛をいただき開催しました。 インターリハ(株)・エン・ジャパン(株)・オルソテック(株)・クオール(株)・セコム(株)・ホシザキ京阪(株)・ワタキューセイモア(株)・榎並工務店・(株)きんでん・(株)ファルコファーマシーズ みのり薬局北山・(株)塩梅なにわ・(株) 岡野組・(株)若藤・(株)洛北義肢・(株)KOGA建築設計室・(株)P.O.ラボ・(株)TSエンジニアリング・(株)エス・ティー・(株)ケイルック・(株)ケルク電子システム・(株)シミズ・ビルライフケア S・BLC関西社・(株)ブルームプロモーション・(株)マサミガーデン・(株)関電エネルギーソリューション・(株)古瀬組・(株)後藤工務店・(株)公益社・(株)小野設備・(株)松本印刷・(株)大林組・(株)長谷川工務店・(株)平安・(株)平塚薬局・京友商事(株)・光星電工(株)・三菱オートリース(株)・三菱電機ビルテクノサービス(株)・新日本ウエックス(株)・新和工産(株)・西日本電信電話(株)・双葉メンテナンス工業(株)・大王製紙(株)・大和電設工業(株)・中辻造園・中辻造園土木工業(株)・朝日衛生材料(株)・日工自動車(株)・日本水処理工業(株)・富士ゼロックス京都(株)・(有)山田自販・(有)モンジュ・(有)湯谷文昌堂(敬称略)