おびやま在宅クリニック(熊本県)院長補佐が来訪 京都大原記念病院グループ施設を見学
5月19日(金)、おびやま在宅クリニック(熊本県)の田代清美院長補佐が、京都の地域包括ケアシステムの現状を知るため、京都大原記念病院グループに来訪されました。 当日は京都大...
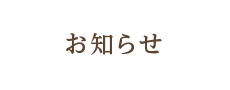
5月19日(金)、おびやま在宅クリニック(熊本県)の田代清美院長補佐が、京都の地域包括ケアシステムの現状を知るため、京都大原記念病院グループに来訪されました。 当日は京都大...
5月15日(月)、京都大原記念病院グループが今春の確定申告の広報活動に協力したことから、児玉博行代表が左京税務署の眞砂剛志署長から表彰状を受けました。 ①同署から依頼を受け...
5月12日は看護の日。近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、日本では1990年に制定されました。 看護の日にちなみ、現場で働く看護師に「仕事のやりがい」について...
5月12日は看護の日。近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、日本では1990年に制定されました。 看護の日にちなみ、現場で働く看護師に「仕事のやりがい」について...
4月29日(土)、京都大原記念病院グループに海外からのお客様が来日されました。アズセナ・グスマンさん(スコットランド エディンバラ大学講師/臨床心理学博士)とサラ・トーレスさん(メ...
認知症になって住み慣れた自宅を離れ、介護施設へ入所することになった本人さんの気持ちはどのようなものでしょう? 私の祖母が認知症になったのは、私が高卒で受験勉強をしていた...
5月15日(月)、葵祭が開催されるにあたり、送迎バスの一部ルート変更をいたします。 出町柳ルート(ロ系1便)において、京都御苑 堺町御門前(御所南リハビリテーションクリニッ...
昭和初期までの約800年にわたる大原の風習に「大原女」があります。かつて、寂光院に入寺して隠棲した建礼門院徳子の侍女にあたる「阿波内侍(あわのないじ)」が原型とされる衣装を身にまと...
京都大原記念病院グループが毎月発行する「広報誌 和音5月号」を発行しました! ★詳しくはこちら
この度、京都大原記念病院のホームページをリニューアルいたしました。 このページをご利用いただく皆さまにとって、より使いやすいページ運営を心掛けて参ります。 今後ともどうぞよ...