【広報誌】和音10月号を発行しました!
京都大原記念病院グループが毎月発行する「広報誌 和音10月号」を発行しました! ★詳しくはこちら
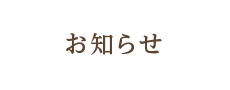
京都大原記念病院グループが毎月発行する「広報誌 和音10月号」を発行しました! ★詳しくはこちら
8月31日(木)、医療法人三九会 三九朗病院(愛知県豊田市)より加藤 真二理事長ら8名が京都大原記念病院グループに来訪されました。これは、京都大原記念病院 副院長 三橋 尚志が愛知回復期リハビリテーションの会で講演した際に出来たご縁で実現したものです。 当日は京都大原記念病院・御所南リハビリテーションクリニック・介護老人保健施設 博寿苑・特別養護老人ホーム 大原ホームの各施設を見学されました。 京都大原記念病院見学時には、病院内にあるデイルームについて、「ご入院患者の症状に合わせた対応ができる設備が準備されていますね。」など、興味をお持ちになりました。看護師長から、具体的にどのような活用をしているか、また利用しているご入院患者のご様子などをご説明しました。 見学後は、京都大原児玉山荘にて意見交換会を行いました。外部病院との連携についてやご入院患者にお出ししているお食事についてなど多岐にわたる議題があがり、弊グループとしても大変勉強になる有意義な時間でした。 外部医療機関からの見学、あるいは視察研修など京都、日本そして海外と視野を広くもつために、今後も積極的に取り組んで参ります。
久多は、京都市街地から車で1時間程度の京都市最北端に位置する、山あいの清涼たる久多川が流れる実に自然豊かな集落である。5町(上の町、中の町、下の町、宮の町、川合町)の集落からなり、いまだ茅葺屋根の民家が点在する日本の懐かしい山里を体験することができる。 春は若葉と山桜、夏は緑豊かな山々、秋は一面の紅葉、冬は時に数mもの豪雪と、四季折々の姿を見せてくれる。夏は冷涼な気候で過ごしやすく、鮎などの釣り人で賑わい、旧田を利用した北山友禅菊の栽培も盛んである。 久多の歴史は古く、平安時代から木材の供給地として知られ、一説には平家の落人が逃れてきたとも言われている。花笠踊りは五穀豊穣・豊作祈願の風流踊りの流れを汲む国の無形文化財に登録されており、この他松上げは愛宕山の献火行事とし毎年8月23日に行われる。 もともと農・林業が産業の中心であったが、最近は、豊かな自然を生かし、キャンプ場などのアウトドア施設が作られたり、京都の農業体験型民宿である、農家民宿(京都市で初めての開業)が営まれ、ジビエ料理をいただくことができる。平成28年1月に富士山が見える最西端の地としても報道され、話題となった。 久多地区の人口は84名(平成27年国勢調査)。高齢化率は61%を超えており、地区内には生活支援としてのお店はなく、公共の交通機関まで10㎞離れているなど、久多地区も言うに及ばず過疎化が進行している地域である。公共の施設として、診療所(週に1度医師会より派遣で開設)と駐在所、そして高齢者の集いの場所として、いきいきセンター(昭和56年休校となった久多小学校を改装)、市出張所、郵便局、駐在所があるのみである。 水源の里・久多は、3回にわたって掲載しました。 水源の里・久多(2) 豪雪の冬は脱出する人も ADL向上が意欲生む 水源の里・久多(3) 自立支援に強いニーズ 近隣の助け合いは今も
京都大原記念病院グループが京都府立医大病院OPENHOSPITAL2017ににブース出展します! 【 日時 】 平成29年9月18日(月・祝) 10:00 ~ 16:00 【 会場 】 京都府立医大病院 当日は京都大原記念病院グループ ブースにおいて、京都大原記念病院グループオリジナル 人参ジャムや玉ねぎドレッシングなどの販売や【タキイ種苗株式会社後援】種子アート体験を予定しております。数量・体験人数に限りがございますので、予めご了承ください。 会場にてスタッフ一同心よりお待ちしております。 ※写真は昨年の様子です -ーー お問い合わせ先 --- 京都大原記念病院グループ (株式会社 ケア・サポート) Tel. 075-744-5020 Fax. 075-744-5025
定員に達しましたので、受付を終了させて頂きました。 多数のお申し込みを頂き、誠にありがとうございました。 55才からの大人のフリーマガジン ritorno(リトルノ)がタイアップし、京都シネマで初開催! [映画 人生フルーツ 鑑賞会 in 京都シネマ ] 自分らしく生きること あなたは、考えたことありますか? 普段考えたことがありそうでない自分らしく生きること しなやかに、自分らしく生きる老夫婦のドキュメンタリー映画人生フルーツを一緒に鑑賞し、感想を交えたトーク会を行います。京都大原記念病院グループのスタッフ、タイアップのリトルノ編集長とともに 自分らしくいきること 改めて考えてみませんか? 詳しくは画像をクリック!
京都大原記念病院グループが毎月発行する「広報誌 和音9月号」を発行しました! ★詳しくはこちら
夏になると風と共に爽やかな香りを放つ赤紫蘇。大原産のものは、山間の環境で守り続けられるもっとも原品種に近いものです。この赤紫蘇となす、塩が漬け込まれ、京都の三大漬物の一つ「しば漬け」が出来上がります。7月から8月にかけて収穫されると、一年分の漬け込みが、一気に始まります。 三千院の参道沿いにある漬物樽が並んだお店が「志ば久(しばきゅう)」です。1945(昭和20)年の創業から、代々受け継いできた伝統を守り続ける、しば漬けが主力の漬物処です。ここで大原のしば漬けについて話を聞きました。 「農家みたいに感じることもあります」。次期代表で創業から4代目となる久保統さん(41)は言います。大原では、どこのお店も赤紫蘇は自分で栽培します。志ば久でも、5反(1反 = 300坪 = 991.74㎡)ほど育てており「種は外から買ってきたものではなく、畑で育ったものを代々受け継いでいる」といいます。 収穫された赤紫蘇は、従業員や季節限定のアルバイト学生らが、手作業でもいでいきます。一緒に漬け込まれるナスは約15トンとのことですから、使用される赤紫蘇も相当な量です。早いものは漬け込みから2~3週間で「新漬け」として店頭に並びますが、中には約1年間漬け込まれるものもあります。日が浅い間は若干ストレートな酸味を持つものが、時間が経つにつれて徐々に角が取れて行く。人それぞれ好みは違うものの、どちらにも根強いファンがいるそうです。 志ば久では、創業以来「志ば漬」と呼ばれています。おもてなしの心を忘れず多くの方に召し上がっていただきたいという“こころざし”から、そう呼んでいるそうです。志ば漬は、店舗、インターネット、東京や京都の百貨店などで購入できます。今後について聞くと「無理な拡大をせず、大原の地に根を張り、がんばっていきたい」と力強く語ってくださいました。 今回の取材は、京都大原記念病院グループオリジナルの三笠「幸福焼」で、赤紫蘇味を志ば久さんと共同開発したことがきっかけで実現しました。弊グループでは今後とも、地元・大原の魅力を発信していきます。
7月28日(金)、京都府看護協会左京地区施設代表者ら11名が京都大原記念病院グループに来訪されました。これは、京都市左京地区の施設が顔の見える関係を構築し、看護力のネットワーク強化を目的に同協会が開催した「左京地区施設 お宅訪問」研修として行われたものです。 京都大原記念病院を見学時には、「回復期病院の様子をなかなか見ることがない。マンツーマンでリハビリを実施し、市街地ではなかなか難しい外周路の歩行訓練や自家菜園で野菜を収穫する様子に驚きました。」「若いスタッフが多く、活気がある。環境が良いのは立地だけではないですね。」などのお声をいただきました。 京都大原記念病院敷地内にある自家菜園では、グリーン・ファーム・リハビリテーション®をご紹介しました。最盛期のミニトマトを収穫したその場で食べていただくと、「オレンジ色のミニトマト(オレンジ千果)がとても甘くて美味しい」「とても食べやすいトマトですね」などと大好評でした。また、「収穫する楽しみだけでなく、育てる楽しみを体験できることが素晴らしい。」と褒めていただきました。 外来リハビリテーションを担う御所南リハビリテーションクリニックでは、”このような患者さんにはこのようなリハビリが提供できる”と事例を紹介すると、「こんな患者さんにはどうですか?」「こんなケースにはどのようなリハビリ提供が考えられますか?」といった具体的な質問が飛び交う、活発な意見交換の場となりました。 地元左京地区施設に所属する看護師さんに弊グループをより知っていただく機会となりました。これを機に、地元左京区の地域医療を支えられるよう、パートナーシップを強めて行けるよう邁進して行きます。
京都大原記念病院が自家菜園を拠点に取り組む農業とリハビリを融合させた「グリーン・ファーム・リハビリテーション®」 の取り組み--- 7月24日からの2日間、京都大原記念病院の患者さん7名が自家菜園で最盛期を迎えた赤紫蘇を収穫し、葉のもぎ取り作業を行いました。参加された患者さんについて、お二方をご紹介します。 参加者のお一人、溝落 正利さんは職員も驚く手さばきで「仕事ではないけれども、昔やっていたから」と話しながら、楽しそうに葉のもぎ取りを進めます。作業中も担当職員と野菜の種類や、栽培時期・料理方法などを話していました。 溝落さんは、リハビリの時間以外にも天気の良い日は自主練習として自家菜園を散策し、野菜の生育状態を確認したり、雑草を抜いたり。入院当初は90度しか動かなかった腕を、今は180度動かして、高い所にある豆も慣れた手つきで収穫しています。 担当の療法士は、「グリーン・ファーム・リハビリテーション®に大変意欲的に取り組まれている。リハビリの時間にお部屋に迎えに行くと、まず野菜の話が始まります。私より詳しい。」と話しました。 もうお一方について、グリーン・ファーム・リハビリテーション®「赤紫蘇ゼリー」はこちら
京都大原記念病院が自家菜園を拠点に取り組む農業とリハビリを融合させた「グリーン・ファーム・リハビリテーション®」 の取り組み--- 7月24日からの2日間、京都大原記念病院の患者さん7名が自家菜園で最盛期を迎えた赤紫蘇を収穫し、葉のもぎ取り作業を行いました。参加された患者さんについて、お二方をご紹介します。 参加者のお一人、野村 彰子さんは口から食べる訓練を始めたばかりでしたが、院内に掲示されたしそゼリーのポスターを見て「ゼリーを食べられるようになりたい」との強い気持ちを持つようになりました。 提供日の前日に担当医が、ご本人の意欲や体調から大丈夫であると判断し、食べることができました。言語聴覚士と一緒に昼食と「赤紫蘇ゼリー」を摂った野村さんは「香りがいいわね。美味しい」「以前から紫蘇の香りが好き。大原の旬の紫蘇を使ったゼリーをいただけて、本当にうれしい」「最近、リハビリで自家菜園に行きはじめたばかり。また紫蘇を見に行きたいわ」と話しました。 また「口から食べると元気がでたわ!」とこれからの嚥下訓練にも意欲を見せていました。 もうお一方について、グリーン・ファーム・リハビリテーション®「赤紫蘇の収穫」は、明日公開します。